 全文ダウンロード(PDF)
全文ダウンロード(PDF)
技術進歩の要因と影響に関する実証研究
青柳直樹 総合政策学部3年
永井秀児 総合政策学部3年
堀田朋也 総合政策学部4年
岡部研究会研究報告書
2000年度春学期(2000年8月改訂)
本論文作成にあたっては、丁寧で親切なご指導をしてくださった岡部光明教授に深く感謝したい。また研究報告会議(7月7-8日; 於湘南国際村)において有益なコメントをしていただいた岡部研究会のメンバーに感謝したい。なお、本論文の第1部(とくに第1部の第4章)は、田中大訓君(総合政策学部3年:s98851ht@sfc.keio.ac.jp)と青柳・永井とで行なった共同研究に大幅な加筆・修正をしたものである。こうした形でこの論文にすることを許していただいた同君に謝意を表する.
電子メールアドレス:青柳s98008na@sfc.keio.ac.jp 永井s98690sn@sfc.keio.ac.jp
概要
技術革新は、経済の発展と成長にとって大きな原動力である。特に米国では近年、情報通信技術(information technology, IT)の革新が歴史的にも例のない物価安定化をもたらすなど、経済変動の基本的パターンを変化させているとの認識が強まっている。また日本を含む主要国でも、ITの動向とその幅広い影響に関心が高まっている。
本論文の第1部では、技術革新のなかでも近年特に注目を集めている情報通信技術革新に関する投資とその影響(特に労働市場および就業構造への影響)について定量的分析を行った。分析は3つの段階による。第一に、労働と資本の代替関係を明示した設備投資関数を推計し、情報関連投資の変動に関する要因分析を行った。第二に、資本ストックを情報関連資本及び非情報関連資本に分割して取り入れた生産関数を推計し、それを用いて各々の資本ストックについて限界生産性を試算した。そして第3に、上記2つの結果に基づき、90年代における情報関連投資に起因する「雇用代替(削減)効果」及び「雇用創出効果」がどれだけ存在したのかを、労働と情報資本の相対コスト要因を明示した雇用関数を用いて推計した。その結果、以下のことが判明した。(1)上記の設備投資関数の推計によれば、情報関連投資には労働代替効果があること。(2)上記の生産関数の推計によれば、情報関連資本ストックの限界生産性は非情報資本ストックのそれに比べ約8.5倍と非常に高いこと。(3)上記の雇用関数の推計によれば、90年代の日本において、上記(1)の情報関連投資による雇用代替効果は、とりわけ中高年ホワイトカラー層及び若年者層を中心にみられたこと。(4)情報関連資本ストックによる雇用創出効果は雇用代替効果を下回っており、このため全体としては雇用の減少につながったとみられること。今後、情報関連投資を拡大していくには、(1)投資環境の改善および情報関連分野支援のための法改正・規制緩和、(2)雇用流動化に備えた中高年労働者の再教育、が必要である。
第2部では、より一般的な視点から技術進歩を取り上げ、それを生み出す要因と変動パターンを統計的手法(時系列分析)によって検討した。技術進歩(全要素生産性:TFP)は通常、経済成長率から資本・労働など要素投入の寄与率を差し引いた残差(ソロー残差)として捉えられる。技術進歩をこのようにTFPの変動として捉えた場合、それは、(1)技術進歩それ自体による変動、(2)技術進歩以外の要因(景気変動、外生的ショックなど)による変動、に分けられる。まず第1に、TFPが、技術進歩に影響すると考えられる経済変数(研究開発投資、教育支出、技術輸入等)によって説明可能かどうかを2つのモデル、すなわち(a)重回帰モデル、(b)カルマンフィルタによって推定した変動パラメータモデル、によって検証した。その結果、(1)それら変数によって大半は説明可能であること、(2)2つのモデルのうち(b)のモデルの方がより高い説明力をもつこと、が判明した。第2に、技術が技術を生み出すという技術の自己回帰的側面は存在するのかどうかを、最も基本的な時系列分析のモデル(ARIMAモデル)で検証した。それによれば、TFPの変動を決定するひとつの要因としてそうした側面がある程度あるとの結果が得られた。第3に、上記の2つの変動(TFPの変動、技術の自己回帰的変動)にどのような周期性があるのかを検討した(スペクトル解析)。その結果、(1)TFPの変動においては5年周期の波が最も強い影響を持つこと(これは日本のこれまでの景気変動が1回平均5年弱であることと整合的)、(2)技術の自己回帰的な動きは、5年から9年で起こっていること(10年以上前に生み出された技術は今の技術の源泉となっているものの、今ある技術を直接的に生み出したわけではない)、が明らかになった。今後、技術進歩率を高めるためには、(a)労働者の質の向上、(b)情報関連資本ストックの蓄積とその質の向上、(c)研究開発投資の奨励、(d)積極的な技術輸入、などが重要になると考えられる。
【キーワード】
情報関連資本ストック、雇用代替効果、雇用創出効果、資本の限界生産性、労働生産性、
TFP(全要素生産性)、技術進歩、状態空間モデル、ARIMAモデル、スペクトル解析、パワースペクトル
【目次】
はじめに
第1部 情報関連投資と労働市場
1.問題意識と本研究の目的
2. 情報関連投資額と情報関連資本ストックの算出
2.1 情報関連投資額の算出
2.2 情報関連資本ストックの算出
3. 日本における情報関連投資のサプライサイドへの影響
3.1 サプライサイドへの波及ルート
3.2 情報化関連投資の経済効果:既存の議論と米国の例
3.3 日本の設備投資
3.4 日本の設備投資関数の推計
3.5 推計結果の分析
4. 情報関連資本ストックが生産に与える影響
4.1 限界資本生産性の推計
4.2 労働生産性の推計とその要因分解
4.3 情報関連資本ストックが生産性上昇に与える効果の推定
5. 情報化投資が労働市場に与える影響
5.1 雇用代替効果
5.1.1 雇用関数の説明
5.1.2 労働代替効果の推計5.2 推計結果の分析
5.2.1 情報関連投資と雇用者数
5.2.2 情報関連投資と労働投入量
5.2.3 情報関連投資と雇用削減効果5.3 雇用創出効果
5.3.1 雇用創出効果の測定方法5.4 情報関連投資と失業者
5.4.1 ホワイトカラー
5.4.2 若年層の失業
5.4.3 新しい就業形態
1. はじめに
2. TFPに関する説明と推計方法
2.2 本稿で扱うTFPの概念
2.3 TFPの推計方法
3. 状態空間モデルによるTFPの推計
3.2 基本モデルの定式化に関する補足説明
3.2.2 雑音の設定
3.3 状態空間モデルの推定(1)
3.3.2 観測方程式の設定
3.3.3 状態雑音と観測雑音の設定
3.4 状態空間モデルの推定(2)
3.4.2 時変パラメータモデルによる推定
3.5 分析と結果の考察
4. ARMAモデルによるTFPの分析
4.1.2 MAモデル
4.1.3 ARMAモデルとARIMAモデル
4.2 モデルの定式化
4.3 モデルによる予測とその考察
5. スペクトル解析
5.2 定常過程Xtのパワースペクトル
5.2.2 パワースペクトルの推定
5.3 ARMAモデルのパワースペクトル
5.4 まとめと考察
6.2 政策提言
補論A. 重回帰モデルによるTFPの要因分解
補論B. 情報関連ストックの推計方法
補論C. 情報関連資本ストックの質の推計方法
補論D. データの出所
参考文献
はじめに
技術革新は、経済の発展と成長にとって大きな原動力である。特に米国では近年、情報通信技術(information technology, IT)の革新が歴史的にも例のない物価安定化をもたらすなど経済変動の基本的パターンを変化させているとの認識が強まっており、また日本を含む主要国でもITの動向とその幅広い影響に関心が高まっている。本論文の第1部では、技術革新のなかでも近年特に注目を集めている情報通信技術革新に関する投資とその影響(特に労働市場への影響)について定量的分析を行った。第2部では、より一般的な視点から技術進歩を取り上げ、それを生み出す要因と変動パターンを統計的手法(時系列分析)によって検討した。
なお、第一部は青柳・永井が執筆し、第二部は堀田が執筆した。
第1部
情報関連投資と労働市場
1.問題意識と本研究の目的
情報技術(IT)革命という言葉が世界中を駆け巡っている。米国においては91年に底を打った景気が現在まで長期拡大を続けており、その牽引役は情報関連投資であったといわれている。このような情報関連投資の経済に与えるインパクトに関しては、これまで米国を中心に数多くの研究がなされており、日本においては篠崎[1999]による日米比較がある。篠崎[1999]によれば、米国における情報化投資の増勢が労働との要素代替要因であったことが確認された。また、情報化投資によって労働代替、とりわけホワイトカラー層との代替が起こっていることを指摘している。さらに、情報関連投資が労働代替的に働き、雇用削減をもたらすものの、それ以上に雇用創出効果が確認でき、結果的には雇用の増大が見られるとも述べている。また、Brynjolfsson and Hitt[1993]の研究によると、このような積極的な情報関連投資が情報関連資本ストックとして蓄積され、その結果、サプライサイドでの生産性の上昇にかなり寄与していることを研究結果は支持している。同様に日本においても情報関連投資によって蓄積された情報関連資本ストックが生産性に大きく関与しているという、サプライサイドの研究が行われている。
現下日本経済を概観すると、経済危機は脱しつつあるものの、いまだ本格的景気上昇には実感が伴わず、「失われた10年」という言葉が尾を引いている。このような日本経済において、米国で実証されている情報関連投資のもたらす経済的インパクトは大いなる意義を持つ先行事例として加味するべきであり、その経済的意義を日本において定量的に分析し今後の方策を考察する必要があろう。
そこで本章では、情報関連投資が日本経済のとりわけサプライサイドへもたらす影響を以下の段階に分け実証的に分析する。第一に篠崎[1999]の資本財の定義に依拠し、直近までの資本ストックを一般、情報関連、非情報関連資本ストック別に計測する。第二にストック調整型の設備投資関数を用い、情報関連投資の要因分解を行う。第三に、コブ-ダグラス型の生産関数を想定し、情報関連資本ストック及び非情報関連資本ストックに関して、それぞれの限界生産性を推計する。そして両者の投資関数及び生産関数の推計結果に基づき、雇用関数を用いて労働市場と情報関連投資との関係を分析する。最後にこれらの研究結果を踏まえ、情報関連投資の増勢に伴って要請されるマクロ経済政策を提言する。
2.情報関連投資額と情報関連資本ストックの算出
米国とは異なり日本では情報関連投資に関する正確なマクロのデータセット等は揃っていない。従って、本研究において推計を行なうためには、まず情報関連投資額を1975年から1999年までの長期時系列で算出し、ここで得たフローを基にストックを積み上げていかなければならない。具体的には篠崎[1999]で用いられている手法により、1999年直近までの情報関連投資額と情報関連資本ストックを独自に算出するという方法を取った。
2.1 情報関連投資額の算出
まず、情報関連投資の定義から始めなければならない。これは、米国と同様な品目に対応させ、出来るだけ比較が可能であるように統一性を持たせるということである。計上すべき具体的な品目は、電子計算機本体、電子計算機付属装置を「コンピューター関連設備」としてまとめ、有線電気通信機器、無線電気通信機器、その他電気通信機器を「通信関連設備」とした。また、複写機、ワードプロセッサー、その他事務用機械を「その他情報関連機器」として計上した。さらに、「電気通信施設建設」を加えた計4品目の合計が情報関連投資である。これを表にしたものが表1である。コンピューター関連設備、通信関連設備、その他情報関連機器の3品目に関しては総務庁から発行されている産業連関表を用いて、国内固定資本形成(民間)に計上されたものを名目情報関連投資額とした。しかし、産業連関表で求めることが出来るのは1990年までであるため、それ以降の動向は、1990年をベースに各品目の内需(生産―輸出+輸入)の伸び率、第一種電気通信事業者の設備投資伸び率で延長することにより、名目値を算出した。また、電気通信施設建設以外の品目の内需に関しては、(株)日本電子機械工業会のデータと電子工業年鑑のデータにより求めた。そして、実質化は、国内卸売物価指数、建設工事費デフレーターを用いて、各品目毎に1990年基準で行なった。このようにして実質情報関連投資額を1975年から1999年の長期時系列で計測した。
以上のようにして求めた日本の情報関連投資は長期時系列で見るとどのような特徴を持つだろうか。図1は実質民間設備投資の伸び率に対する情報関連投資の寄与度を示している。ここで非常に興味深い事実は、1993年からの数年間において設備投資が調整局面に入り、伸び率が前年を下回る水準で推移しているのに対して、情報関連投資に関しては、全体の設備投資に先駆けて増加傾向に転じている、ということである。しかしその後、1995年から97年にかけて設備投資全体が増勢に転じているのにも関わらず、情報関連投資は失速していることが分かる。
2.2 情報関連資本ストックの算出
次に、実質情報関連投資額から情報関連資本ストックを求める。ストック推計のためにはフローの時系列データに加え、除去率、基準年次のストック量が定まれば、以下の式から情報関連資本ストックが算出可能である。
![]()
それでは,こうして算出した日本の情報関連資本ストックにはどのような特徴があるだろうか。1999年の実質情報関連資本ストックはおよそ93兆5700億である。また、一般資本ストックに占める割合は8.74%で、非情報ストックに占める割合は9.58%である。図2を見ると解るように、情報関連資本ストックは1980年代後半からの蓄積が著しい。また、ストックの伸び率に関しても、1980年代後半に情報関連投資が急増したためにその蓄積率が高まったが、1990年代に入り、設備投資の低迷を受け、情報関連投資もまた縮小し、ストック蓄積率が低下していることがわかる。
3.日本における情報関連投資のサプライサイドへの影響
米国経済は1991年3月よりインフレなき高成長、景気の長期拡大を続けている。情報技術革新による潜在成長率の高まりなどが盛んに議論されるようになり、「米国型経済モデル」が注目されている。確かにこの数年、長期停滞から立ち直りきれない日本、通貨危機の打撃が大きい東アジア、高い失業率に悩まされつづけるヨーロッパという世界各地の深刻な経済状況との対比において、インフレなき成長を維持する米国経済のパフォーマンスは注目の的である。
一般に今回の米国における景気の長期拡大は、情報関連設備投資によってもたらされたと言われる。こうした情報化関連投資により米国経済に蓄積されている情報関連ストックの増大が様々な局面で経済効果を実証した報告も数多く見られる。本論に入る前に、こうした情報関連ストックの増大がマクロ経済にどのような経路で影響を及ぼすかを、供給面に焦点を当て整理しておきたい。
3.1 サプライサイドへの波及ルート
供給サイドにおける最大の効果は、情報化関連資本ストックの普及それ自体が労働代替的な省力化効果を持つということである。つまり、情報関連資本ストックはそれまで労働者が行っていた作業を代替し、企業活動の際に必要な労働投入を軽減するという効果が期待できる。また、それだけでなく他の資本設備や労働力とのシナジー効果を発揮しつつ、生産性上昇に寄与する点も指摘できる。具体的には情報資本ストックは、情報伝達の迅速化や情報の共有化を通じて、人員管理や在庫管理費用など間接コストを抑制する効果がある。また、組織の効率化、意思決定の迅速化をもたらす。組織の効率化を進める過程では、技能の高い労働力を生み出す一方で、生産性のより低い労働力を代替する効果も期待される。また、情報化技術を利用することにより、利益率の低い割高な資本設備の取替えにかかる時間が短縮化されるほか、在庫管理の効率化により、設備稼働率の変動が小さくなるため、既存の生産施設が有効に活用できる。つまりピーク時の対応のためだけに生産設備を余分に増設しておく必要がないのである。このため、企業の設備投資活動に負の影響を与えると考えられる、ストック調整が短縮され、不良設備を保有せずに生産活動を行うことが期待できる。加えて、上記のようなメリットの獲得を目指してますます多くの企業が新技術を開発し導入していくことによって、既存の財・サービスが一段と安い価格やより高い品質で供給される。これらの企業の財・サービスを資本や中間投入として使用する企業にも効率性の向上が波及していくという相乗効果もあろう。
3.2 情報化関連投資の経済効果(既存の議論と米国の例)
情報化関連投資の投資効果、経済性については80年代から盛んに議論されており、いくつかの企業における成功例も紹介されている。しかし一方で情報関連システムの導入が当初期待された効果を達成できていないという指摘も数多く見られる。とりわけ日本における情報化関連投資は、旧態依然とした横並び体質から行われ、その蓄積資本が有効に活用されるための人材教育が追いついていないという、人的能力の欠如といった面の指摘は注目されている。
たとえば米国において盛んな議論を呼んだソロー・パラドクス、つまり生産性のパラドクスといわれる情報技術の経済効果に対する疑念が80年代から90年代半ばに欠けて多勢を占めていた。とりわけ80年代になされた数多くの実証研究では生産性上昇について明確な効果が検証できずにいた。しかし他方、90年代中盤から、情報技術革新のプラス効果を実証的に検証する研究成果があらわれ始めた。米国商務省の最新のアニュアル・リポート「Digital
Economy 2000」では近年とりわけ90年代末ごろから、それまで生産性上昇について懐疑的であったいわゆる「ニューエコノミー否定論者」の多くが、比較的肯定の立場を取りつつあることを報告している。つまり、米国において情報化関連投資およびそこから蓄積される情報化関連資本は、サプライサイドの活性化をもたらし、生産性上昇およびインフレなき継続的成長を可能足らしめる根元であると認識され始めているのである。
3.3 日本の設備投資
しかし、今日の日本経済を眺めると、90年代はまさにバブル崩壊の後処理に追われて、民間設備投資は第一オイルショックの頃にもまして長期低迷していた。バブル期の過剰設備投資がもたらすストック調整の増大、および企業のバランスシート悪化による経済活動の鈍化は、90年代の日本経済における特徴であった。
日本経済は同時に「ストック調整期間の長期化」、「グローバル化の一層の進展」、「情報技術の急激な革新」、という三つの重要な転換期に直面していた。このような背景としての転換期において民間設備投資が低迷していることの問題点は以下の二点に集約されよう。まず第一に、民間設備投資は単に需要項目として景気変動に影響を与える、といった点に留まらず、投資による資本の蓄積が中長期的に将来の日本経済のサプライサイドへも影響するという点である。投資された資本は企業内部に蓄積され資本ストックとして企業活動に利用される。こうして積まれた資本ストックは、中長期的なストック調整を持って減耗していくが、その蓄積が企業活動に及ぼす影響は大きい。第二点目は、近年の情報技術の飛躍的進歩は、最新のテクノロジーを企業内に取り込む形での「資本への体化」が可能になる(熊坂・峰滝[2000])といったことである。例えば、情報化関連投資により、蓄積された資本ストックが、最新テクノロジーによる効率的な企業経営の下支えになることが考えられよう。
加えて近年の「ITブーム」ともいうべき情報化の与えるインパクトへの注目を考えると、バブル崩壊後の長期にわたる景気低迷およびそれに続く回復力の弱い景気上昇のなかで強力な牽引力に欠けて日本の情報化関連投資が日本経済、とりわけサプライサイドに及ぼした影響を定量的にファクトファインディングし、実証分析を行うことが必要である。
3.4 日本の設備投資関数の推計
そこで、情報関連投資が日本経済に及ぼしたインパクトを以下の設備投資関数を用いることで推計する。とりわけここでは、設備投資の要因を、(1)需要の変化に応じて適正な資本ストック水準を調整するために引き起こされる「ストック調整要因」及び、(2)労働と設備の相対コストによって引き起こされる「要素代替要因」とに分解し推計する。また、非説明変数となる設備投資は、設備投資全般(以下、一般設備投資)を、情報関連投資及び非情報関連投資に分けたうえで、以下のように設備投資関数の推計を行った。
これらの設備投資関数では、企業の行動に対し2つの仮説をおいている。第一に、企業は現状の需要動向をもとに将来必要と思われる最適な資本ストック水準と実際の資本ストックの差を数期間にわたって徐々に解消されるように投資水準を決定する(ストック調整原理)。第二に、労働力と資本設備という生産要素のコストを比較し利潤を最大化させるべくコストの高い要素投入を押え、コストの低い要素投入を増やすような組み合わせとなる投資行動を行う。また、この定式化の中では、需要量増減との関係で能力増強投資としてストック調整が進められ、要素代替型の投資はこれとは独立して相対コスト(w/r)の比較により行われると想定している。推計結果は以下の通り。
Ⅰ.設備投資関数
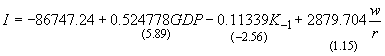
(I:実質設備投資額、GDP:実質国民総生産、K:民間資本ストック、W:雇用コスト、r:資本コスト)
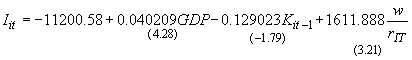
(Iit:情報関連投資額、Kit:情報関連資本ストック、r‐it:情報関連資本コスト)

(Inon-it:一般設備投資額、Knon-it:非情報関連資本ストック、rnon-it:非情報関連資本コスト)
3.5 推計結果の分析
設備投資関数及び一般設備投資関数において、ストック調整要因に関してのt値は充分に高いが、労働代替要因に関してはt値が低く統計的に有意な説明力を持たなかった。情報関連投資関数に関しては、反対に、労働代替要因の統計的有意性は充分であったものの、ストック調整要因に関しては統計的に有意な説明力を示さなかった。この事は二つのことを示唆していると推察できる。第一に、情報化関連投資に関しては、需要動向の伸びに伴って必要とされる情報資本ストック量が増加し、これが投資全体の牽引役となったのではなく、情報資本コストに比べて、労働コストが高いため、要素代替を目的とした投資がなされた。第二に、情報関連以外の一般設備投資に関しては、労働の代替要因は作用せず、むしろ通常のストック調整要因によって変動している。とりわけ旧態依然とした日本の雇用慣行では労働投入の調整は労働者削減というよりむしろ労働時間の削減による調整が為されており、その影響が大きいものと推察できる。
前述第一の点に関し、篠崎[1999]では、バブル崩壊による債務負担の増加、つまりバランスシートの悪化を要因の一つとして考慮し、代理変数として債務償還年数を用いた設備投資関数の推計を行っている。推定結果は本稿における単純なストック調整型設備投資関数よりも説明力の高いものとなり、債務償還年数の長期化は企業の設備投資行動にマイナスの影響を与えることを実証している。
これまでは、情報化関連投資が引き起こすであろう経済効果をサプライサイドを中心に概観してきた。さらに米国における設備投資が牽引力となった長期の景気拡大(ニューエコノミー論)について触れ、対照的な日本の姿を指摘した。以上の背景を前提として日本における設備投資関数を導出し、設備投資全般、情報関連投資、非情報関連投資の3側面から推計を行い、情報化関連投資には労働代替効果が見られる、という点と、その他の設備投資は長期間にわたるストック調整要因に足を引かれる状況にあることを指摘した。
以降、こうして蓄積された情報資本ストックが日本経済に及ぼす影響を、労働生産性、及び雇用への影響という観点から定量的に分析を行う。
4.情報関連資本ストックが生産に与える影響
今までの議論は、需要項目としての企業の設備投資行動に着目した分析を行ってきたが、言うまでもなく、設備投資は需要面だけではなく、設備投資が資本ストックとして蓄積されることを通じて、経済のサプライサイドにも影響を及ぼす。したがって、情報関連投資がサプライサイドに対して与える経済的効果も合わせて行う必要がある。だが、情報関連投資がサプライサイドにどのように影響を与えているかを議論するためには、まずは情報関連資本ストックの量を試算しなければならないだろう。先にも述べた通り、情報関連資本ストックは1990年代に急激に増加し、一般資本ストックに対する比率は1999年には、9.58%にまで達した。この数字は、米国と比較すると依然としてかなりの低水準にあるものの、90年代の情報関連資本ストック蓄積の趨勢から、確実に日米の格差は縮小傾向にあると言えるだろう。以下では、先に算出された情報関連資本ストックから、情報関連投資が日本の経済成長に対してどの程度貢献しているのか、また、限界資本生産性や労働生産性という観点から、生産関数を用いて、サプライサイドに与える影響を実証的に分析を行う。
4.1 限界資本生産性の推計
まず、非情報関連資本ストックと、情報関連ストックのそれぞれについて、限界資本生産性にどの程度差異があるのだろうかという観点から分析を始めたい。
この推計には資本ストックを非情報資本ストックと情報関連資本ストックとに分割した生産関数を想定し、一次同次(α+β+γ=1)であると仮定した上で、以下のようなコブ・ダグラス型の生産関数を用いた。
![]()
(GDP:実質国民総生産、Knon-it:非情報資本ストック、Kit:情報関連ストック、L:非農業雇用者数)
*KnonIT、Lに関してはそれぞれ稼働率、労働時間を乗じ、Kitに関しては稼働率を100%と仮定した。
限界資本生産性を得るには、一般資本ストックの弾力性αと情報関連資本ストックの弾力性βを求める必要がある。したがって、それぞれの弾性値を求めるために、生産関数を次のように変形して、推定した。
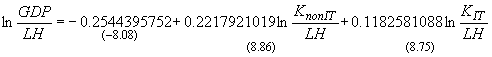
(GDP:実質国民総生産、Knon-it:非情報資本ストック、Kit:情報関連資本ストック、LH:労働投入量)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2.一般資本ストックと情報関連資本ストックの限界生産性
だが、この限界資本生産性の格差は正に情報関連資本ストックの蓄積が十分ではないことを示している。というのは、限界資本生産性が均等になるような資本蓄積が望ましいため、この格差を解消するために、限界資本生産性の高い情報関連資本ストックの蓄積が一層進むと考えられるのである。先ほど見た通り、1990年代に入って急速に情報関連資本ストックの蓄積が進みつつあり、このような趨勢から判断すると、現在は資本蓄積においてその過渡期にあるといえるだろう。しかし、情報関連資本を活用するためにかかるコスト(例えば再教育であるとか)が大きいために、こうした格差が生まれていると考えられる。米国の今回の景気拡大局面においては、限界生産性が高い情報関連資本の蓄積が急速に進み、その結果としてのサプライサイドの活性化が大きな、そして高い成長率を伴った経済成長に好影響を与えているという見方が強い。日本もできるだけ情報化投資に対するリスクやコストを減らし、情報関連資本ストックを増大させるような方向性を示す時期に来ているのだ。
4.2 労働生産性の推計(労働生産性の要因分解)
次に、情報関連投資は労働生産性の上昇に対してはどのように影響を与えたのかに関して、先の式をさらに変形して以下のような推定を行った。以下の定式化の中では、労働生産性(非説明変数=GDP/L)の変化を、非情報関連設備装備率(K0/L)の変動要因と、設備の情報化(KI/K0)変動要因で説明している。
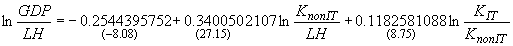
| 労働生産性
(GDP/LH) |
非情報資本設備率要因
(Knon-it/LH) |
設備の情報化要因
(Kit/Knon-it) |
その他の非設備要因 | |
| 75~99年率 |
|
|
0.590 | -0.000 |
| 77~80年率 |
|
|
-0.394 | 0.0063 |
| 83~85年率 |
|
|
-0.004 | -0.010 |
| 86~92年率 |
|
|
0.855 | 0.001 |
| 93~97年率 |
|
|
0.484 | -0.000 |
表3.労働生産性の要因分解
4.3 情報関連資本ストックが生産性上昇に与える効果の推定
とはいえ、上記の結果からのみで、情報関連資本ストックが労働生産性の上昇に全く関与していないと結論づけるには早計ではないだろうか。そこで、一般資本ストックと労働投入に関して、一次同次を仮定し、以下のような情報関連資本ストックが増加することで、一般資本ストック・労働の生産性が上昇するという生産関数を想定する。
![]()
(GDP:実質国民総生産、KnonIT:非情報関連ストック、Kit:情報関連ストック、L:非農業雇用者数)
*KnonIT、Lに関してはそれぞれ稼働率、労働時間を乗じ、Kitに関しては稼働率を100%と仮定した。
上記式を以下の通りに変形し、この式を推定した。
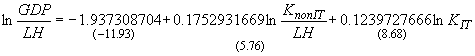
(GDP:実質国民総生産、KnonIT:非情報関連ストック、Kit:情報関連資本ストック、LH:労働投入量)
情報関連設備投資が雇用に与える影響には、非情報関連設備投資が雇用に与える影響とは異なる特徴が存在している。両者は共に、設備投資によって新たな産業分野の成長を促すことで新たな雇用を生み出すという雇用創出効果を持っている一方で、企業が生産性を向上させる目的で行うリエンジニアリングと結びついている。そのため、生産性の向上を目的とした情報化投資によっては労働から資本への要素代替が行われ、要素代替によって雇用削減同時に達成されるのである。設備投資の要因分析で説明されているように、情報関連投資は需給動向に伴って必要とされるストック調整を目的として増加したのではなく、情報資本コストに比べて労働コストが高いために要素代替による効率化を目的として増加したものなのである。以上より、雇用が労働市場に与えるマクロの影響を分析するためには、情報化投資による雇用創出効果だけではなく、労働代替による雇用削減の効果についても明らかにする必要がある。
5.1 雇用代替効果
5.1.1 雇用関数の説明
それではまず、情報関連投資が労働市場に与える影響のうち、労働代替による雇用削減効果を明らかにするために、費用最少化モデルより労働需要関数を導出して、情報資本コストと労働コストの相対価格の変化が労働市場にどのように影響を与えるのかを、情報関連投資の増勢が顕著に見られた90年代を中心に計測する。本研究で使用する労働需要関数は、労働コスト(w)と情報資本コスト(r it)の相対価格、労働コストと非情報関連資本コスト(r non-it)、生産量(GDP)、1期前の雇用者数(L(-1)) および 労働投入量(LH(-1))という4つの変数の変化で労働需要の変化を説明して行くものである。
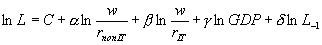
労働と代替関係にある資本コストと比較して労働コストが高くなると、一定の生産水準においては費用を最小化しようとするために労働需要は減少し、代替効果として資本への需要(すなわち設備投資)は増加していく。また、生産水準が増大すれば労働需要は増加していくものである。故に、想定される符号条件は、α、βが負、γが正である。しかし、以上の関数に基づいて計量分析を行った結果、情報関連設備投資が労働代替効果を示したのに対し、非情報関連設備投資において労働代替要因が有意な説明力を示さなかった。この結果については、生産要素間の代替関係に先見的な制約を持たないトランスログ型生産関数を用いて、情報資本と一般資本と労働との代替の弾力性を計測した実証研究(中西・篠崎[1998])によると、代替の弾力性は情報資本と一般資本の間で最も高く、一般資本と労働との間で最も低いことが検証されている(表4)。また、本研究で行っている設備投資関数の分析でも、非情報関連設備投資において労働代替要因が有意な説明力を示していないことを考えると、非情報資本と情報資本のそれぞれが独立に労働と代替するのではなく、非情報資本が情報資本に代替されてさらに労働が情報資本に代替されることで資本の雇用代替が起こっていると考えることができるだろう。そして、この考え方に従って以下のような労働需要関数が導出されるのである。
![]()
| ESKC | ESCW | ESKW | ||||||
|
1977
|
1.6193
|
0.2346
|
0.1071
|
1987
|
1.6282
|
0.2590
|
0.3272
|
|
|
1978
|
1.6278
|
0.2413
|
0.1340
|
1988
|
1.6267
|
0.2592
|
0.3473
|
|
|
1979
|
1.6413
|
0.2405
|
0.1568
|
1989
|
1.6319
|
0.2599
|
0.3596
|
|
|
1980
|
1.5993
|
0.2384
|
0.1748
|
1990
|
1.6288
|
0.2593
|
0.3768
|
|
|
1981
|
1.6077
|
0.2444
|
0.2003
|
1991
|
1.6298
|
0.2590
|
0.3925
|
|
|
1982
|
1.6078
|
0.2470
|
0.2214
|
1992
|
1.6263
|
0.2581
|
0.4065
|
|
|
1983
|
1.6106
|
0.2500
|
0.2425
|
1993
|
1.6211
|
0.2569
|
0.4192
|
|
|
1984
|
1.6155
|
0.2531
|
0.2642
|
1994
|
1.6292
|
0.2562
|
0.4338
|
|
|
1985
|
1.6133
|
0.2542
|
0.2831
|
1995
|
1.6379
|
0.2550
|
0.4480
|
|
|
1986
|
1.6125
|
0.2571
|
0.3062
|
C:一般資本 KC:情報資本と一般資本
(出所)中西・篠崎[1998]
5.1.2 労働代替効果の推計
労働需要関数に基づいた計量分析にあたっては、労働コストを雇用者数1人あたりの所得を基準とした場合と、労働投入量あたりの所得を基準とした場合とに分けてそれぞれ分析を行った。情報関連投資による雇用削減は、雇用者の増減によってのみでなく労働時間の調整を通して行われることがあるため、両方の分析を行うことで情報関連投資が労働市場に与える影響をより正確に分析できると考えたからである。
(Ⅰ) 情報関連投資と雇用者数
情報関連投資が雇用者数の増減に与えた影響を分析するために、労働需要関数の推計を行う。この分析にあたっては、労働コストは雇用者数1人あたりの雇用者所得を使用し、資本コストについては情報関連、一般それぞれの資本財価格(デフレーター)と割引率要因、金利要因から計算された資本コストを使用した。労働需要は雇用者数、生産量は国内総生産を使用し、年次ベースで75年から99年までの期間を推定した。その結果、雇用関数1に関しては、説明変数相互間の多重共線性の問題で説明変数の優位性が低く、推計期間によっても係数が安定していなかったが、雇用関数2に関しては、多重共線性の問題が解決された。
さらに、情報関連投資による影響を明確にするために、雇用者総数1人あたりの雇用者所得ではなく非農業雇用者総数1人あたりの非農業雇用者所得より労働コストを求めることによって、以下のように推定結果が求められた。(全産業の雇用者数を対象とせず、非農業雇用者のみを対象として行った推計結果の方がいずれの変数も高い説明力を示したということは、情報関連投資は非農業を中心に行われているということである。情報関連投資によって非農業部門での効率化・生産性上昇がもたされることが考えられにくいことから、本研究では分析の対象を非農業部門に限定していくことにする。)
![]()
(L:非農業雇用者数、GDP:実質国民総生産、w:非農業雇用者所得、R it:情報資本コスト)
情報関連投資が労働投入量の増減に与えた影響を分析するために、再び労働需要関数の推計を行う。この分析にあたっては、労働コストは労働投入量(雇用者数×総実労働時間)あたりの雇用者所得を使用し、資本コストについては情報関連、一般それぞれの資本財価格(デフレーター)と割引率要因、金利要因から計算された資本コストを使用した。労働需要は非農業雇用者数と総実労働時間、生産量は国内総生産を使用し、年次ベースで75年から99年までの期間を推定した。その結果、労働コストに雇用者数1人あたりの雇用者所得を用いた場合と同じく、雇用関数1に関しては、説明変数相互間の多重共線性の問題で説明変数の優位性が低く、推計期間によっても係数が安定していなかったが、雇用関数2に関しては、多重共線性の問題が解決された。
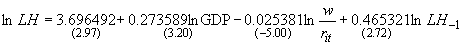
(LH:非農業労働投入量、w:労働投入量あたりの雇用者所得)
5.2 推計結果の分析
5.2.1 情報関連投資と雇用者数
以上までの推計結果に基づいて、労働コストと情報資本コストの相対価格の変化が、80年代および90年代の雇用に与えた影響を算出すると、情報関連投資による代替効果によって、80年代に38.5万人、90年代に100.7万人の雇用(非農業)が削減されていることが確かめられた(図5)。情報関連コストの低下が雇用者数の削減と明確に結びついているという結果からは、情報関連投資には労働に対して代替弾力性の高い効果が多く含まれているということが指摘できる。
また、90年代の情報関連投資は、80年代に比較して2倍以上の雇用削減効果をもたらしたということは、90年代に入って情報資本コストの労働コストに対する相対価格が急激に下がった(図4)ということが大きかったのだと考えられる。労働コストが80年代および90年代を通じて増加を続けているのに対して、情報資本コストは90年代に入って急激に低下している(図3)ことから、90年代の雇用削減は特に情報資本コストの低下によってもたらされたのだということが確かめられる。情報資本コスト低下の要因としては、CPUの能力が急上昇したことでより廉価で高性能なPCの生産が可能になり、同時にMosaic(1993)やNetscape(1995)のようなWWWの閲覧ソフト(ブラウザ-)が開発されたことで、PCとInternetの利用が拡大したということが大きかったものと推測される。
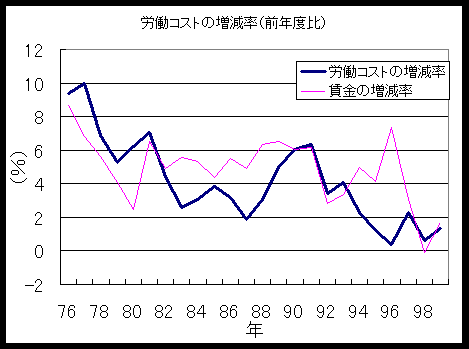
図3.労働コストの増減率
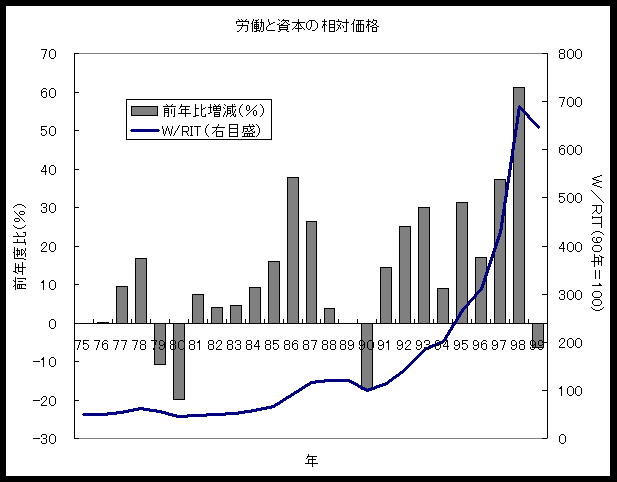
図4.労働と資本の相対価格
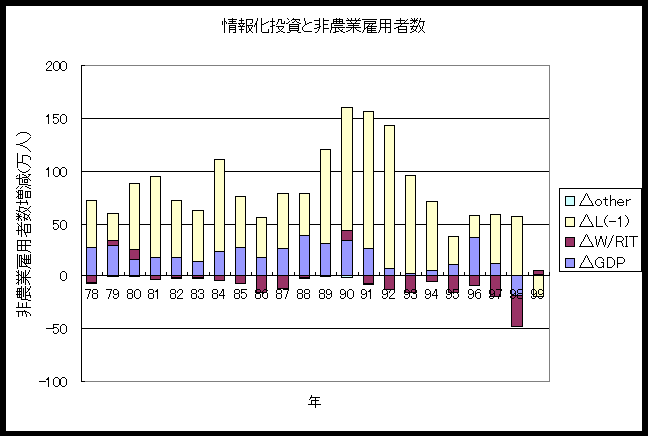
図5によると、GDP経済成長率の増加によっては80年代に224.7万人、90年代に115.5万人の雇用創出効果があったものと考えられる。バブル崩壊以降の低成長(3年連続のゼロ成長、98年のマイナス成長)によって、経済成長による雇用確保・維持というものが難しくなってしまったのである。雇用者数の調整速度(α)が0.199と遅いことからは、雇用者増減による雇用調整の進行は80年代、90年代を通じて非常に遅かったのだということが確かめられる。
5.2.2 情報関連投資と労働投入量
次に、労働コストと情報資本コストの相対価格の変化が、90年代の労働投入量に与えた影響を算出すると、情報関連投資による代替効果によって、労働投入量にして37769だけの労働需要が削減されたことが確かめられる(図6)。(総実労働時間を一定とした場合に)220万人程度の雇用削減が得られたという試算になり、90年代の雇用調整の半分以上は、労働時間の調整によって回避されてきたものであると言うことができる。
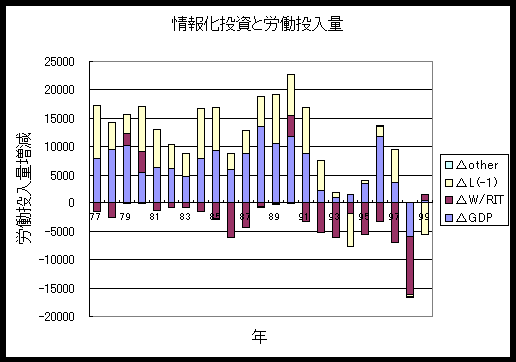
また、GDP経済成長率の増加によっても、労働投入量にして38885だけ労働需要が増加したことが確かめられる。(総実労働時間を一定とした場合に)230万人程度の雇用が創出されたという試算になり、労働需要の変動に対しては、人員整理だけではなく労働時間の調整で対処しているということが明らかになるだろう。また、雇用の調整速度(β)が0.558であることから、雇用調整に際しては雇用者数の調整によってではなく、労働時間の調整によって労働需要の変動に対応することで雇用の安定をはかっていたということが確かめられる。
5.2.3 情報関連投資と雇用削減効果
以上の投資関数の推計結果から確かめられることは、情報関連投資が
業務の効率化を可能にすることで雇用削減を可能にしてきたということだけではない。雇用安定を優先させるために、雇用者数の調整を回避してきたということが確かめられるのである。雇用者数の調整速度(α)が遅かったために、(総実労働時間を一定とした場合に)雇用安定の目的で104万人だけしか労働需要が発生しない計算のところで
雇用安定のために674万人もの労働需要が発生していたということから、500万人程度の雇用が削減されていたところを、労働時間の調整や労働生産性の低下を許容することで回避してきた、ということが確かめられる。このような傾向は、短期的に考えれば
雇用安定ということから良い効果があったということができるが、逆を言えば、情報関連投資に対応した
新しい雇用の形態を描くことができずに 不採算部門を抱えたままで生産性の向上を妨げているという風にも捉えることができるだろう。
5.3 雇用創出効果
5.3.1雇用創出効果の測定方法
次に、情報関連投資が労働市場に与える影響のうち、情報関連投資が新たな産業分野の成長を促すことで新たな雇用を生み出すという雇用創出効果を明らかにする。雇用関数で明らかにしたGDP増加要因による雇用創出の内訳には、情報関連投資によって促された成長も含まれている。そこで、GDP増加の要因分析を生産関数を推定することによって行い、そこに占める情報関連投資の寄与度および前出の雇用関数から、情報関連投資による雇用創出効果を測定する。これまでの分析は、あくまで需要項目としての情報関連投資とそこからの波及効果の測定であったが、ここでは設備投資の結果がサプライサイドに与える影響を考えなければならない。具体的には、情報関連投資が情報関連ストックとして蓄積されるという経路を通じて経済のサプライサイドに影響を与え、資本生産性および労働生産性の上昇が達成されていくということである。
情報関連投資の投資効果、経済性については80年代から盛んに議論がなされており、80年代に数多く成された研究では労働生産性の上昇等について明確な効果が検証できなかったため「生産性のパラドックス(Productivity Paradox)」と評されていた。コンピューターなどの情報関連資本の陳腐化も速く、ストックベースでのシェアが他の一般資本ストックに比べて小さいため、情報関連投資がサプライサイドに与える効果はあまり無いという指摘もある。しかし、Brynjolfsson and Hitt[1993]による研究のように、情報関連ストックの限界資本生産性の分析で情報関連投資の資本収益性は非常に高いという計測結果が出ている例もあり、ストックについて情報関連投資と一般設備投資とに分けた生産関数から、それぞれの限界資本生産性の計測を行うことができると考えられる。
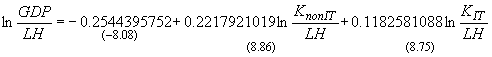
(GDP:実質国民総生産、Knon-it:非情報関連ストック、Kit:情報関連資本ストック、LH:労働投入量)
5.4 情報関連投資と失業者
以上までのところで、情報関連投資がマクロの雇用に与える影響を分析してきた。そこで次に情報関連投資の影響を強く受けている特定の集団について考察していきたい。
5.4.1 ホワイトカラー
情報関連投資による雇用削減の特徴としては、従来の設備投資では代替が容易ではなかったホワイトカラーによる労働との代替という側面が強いということが挙げられる。実際、雇用削減効果が最も強く働いた90年代後半にはホワイトカラーの雇用者数が100万人程度の削減を見せており(図7、8)、今後3年間についても企画管理部門のホワイトカラー労働者が雇用削減の最も有力な対象であるということが明らかになっている。そして、その中でも最も厳しい状況にあるのが、雇用削減の中心となる中間管理層に多い中高年層(特に50代)である。情報の収集・整理と伝達とをその主たる業務分野としてきたために、コンピューターによるネットワーク構築によって労働を資本に代替しやすいのである(図9)。
図9.雇用過剰感のある年代
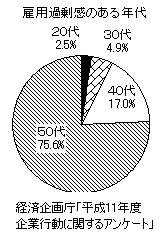
また、以下は40歳から54歳の就業者についての労働需要関数の推定結果である。この結果からも、中高年層の労働者について情報関連投資による雇用代替効果が強く作用していたということが確かめられる。
![]()
(L40-54: 就業者数40歳~54歳、GDP: 実質国民総生産、 W: 労働コスト、 r-it: 情報関連資本コスト)
![]()
(L25-39: 就業者数25歳~39歳、GDP: 実質国民総生産、 W: 労働コスト、 r-it: 情報関連資本コスト)
5.4.2 若年層の失業
情報関連投資の増加によって雇用が削減されたホワイトカラーと反対に、情報関連投資の増勢にもかかわらず雇用調整が進展しないために影響を受けているのが、若年齢層の失業者の増加である(図10)。雇用者数の調整速度(α)が0.199と遅く、雇用代替以外を目的とした情報関連投資については未だに増勢が見られていないということがあって、産業全体として失業者が増加している。これは、情報関連資本ストックの蓄積を進行させるためには、企業が情報化を推進していく際に、業務フローや組織体制そのものが情報関連資本を効率的に利用する形態に変わっておらず、情報関連投資の投資目的が達成されにくい状況にあるということに起因している。その負担を負っているのが前述した中高年層のホワイトカラーと若年層(新卒の未就職者が中心)である。金融機関の破綻などによって本格的に雇用不安が起こってきた90年代後半に、最も厳しい処遇を受けているのが若年層の労働者であることは年齢別失業率の推移からも明らかであり、この10年間で学卒未就職者がおよそ2倍に達している(図11)ことを考えると、早急に対策を講じていく必要がある。
15歳から24歳の若年層就業者数については、労働需要関数から景気変動および情報化投資による影響を強く受けやすいという結果が確かめられる。この結果が示しているのは、雇用調整が進む際にその対象となりやすい年齢層であるということである。情報関連投資が増加した結果、(レイオフではなく、新卒学生の就職難などで)雇用削減の対象となったのも若年層であり、情報関連投資に起因する雇用創出効果が本格化していないために失業者数を増やしつづけているのも若年層である。
![]()
(L15-24: 就業者数15歳~24歳、GDP: 実質国民総生産、 W: 労働コスト、 r-it: 情報関連資本コスト)
5.4.3 新しい就業形態
もちろん、雇用者数が削減される一方で、情報処理能力が高い労働者へのニーズは急増してきている。政府や大企業のスリム化に対応して、従来までホワイトカラーが担ってきたような業務を効率的に代替する外部委託産業である。情報化を推進し、企業のスリム化を達成しながらに新たな労働需要を発生させることができるという点で情報化の進展に伴って成長が期待される産業分野である。しかし、日本では依然として企業ごと自治体ごとの雇用調整が行われており、人材派遣・人材紹介業務の自由化が行われたのも99年12月のことである。90年代後半の情報関連投資による雇用創出が60万人程度に留まっていることからも、現時点では外部委託産業は発展途上の段階にあるものであるが、今後において新しい労働環境が整備されることを通じて外部委託産業が成長していけば、情報関連投資による企業のスリム化に伴って外部委託産業が活用されていくことになり、情報関連投資も本格的な増勢に向かうことになるだろう。
6.政策提言
これまで、情報関連投資がどのような要因で行われてきたのか、そして情報関連投資によってもたらされた情報資本ストックはどのくらいの生産力を有し、労働生産性にどの程度寄与しているのかについての結果が得られた。また、情報関連投資によって、雇用代替がどのくらいの規模で進んできているのかについても定量的な分析により明らかになった。この結果から、総じて言えることは、少子化・高齢化によって労働力不足が懸念される21世紀において我が国が持続的な成長を続けていくためには、情報化投資を拡大し、情報関連ストックを蓄積していくことが不可欠であるということである。上記の分析から情報関連投資は労働代替的に作用するならば、労働力人口が減っていく21世紀以降も、経済成長率を少なくとも維持しながら安定的な成長ができることを示しているように思われる。だが、生産性をより高めるためには、それに最大限のパフォーマンスを発揮できるような政策デザインが望まれるのではないか。そこで、これまでの分析から導き出された結果から政策提言を行う。
第一に政府が取るべき政策は、いわゆる「情報インフラ」を早急に全国に整備し、それを安価で使用できるようにして、ITへの参入に対する敷居を低くするという政策が考えられる。幸いなことに、もはやフロンティアと思われていた私たちには「米国におけるIT革命の成功」というモデルがある。米国に倣い、情報インフラ整備のための障壁となっている種々の規制の撤廃を促し、民間主導でIT革命を引っ張っていけるようにサポートしていかなければならないだろう。労働市場の流動化にテコ入れをしていくという観点からも、積極的に情報関連投資を行わせるための政策を実施するべきである。その一例としては、情報関連投資に対しての投資減税などが考えられる。今後も、情報関連資本のレンタルコストは低下していくものと考えられるが、情報関連投資に絞って投資減税を行うことで資本ストックの情報装備率を上昇させ、資本ストック全体としての限界生産性を向上させるということで経済成長を促していくことができるだろう。
また、今日のような急速な情報化の進展は、効率化・生産性上昇をもたらす可能性があるが、他方でこの変化に対応できない人々が取り残される危険性があるので、リテラシーの教育を中心に中高年を対象とした支援を行っていく必要がある。再雇用のために教育を受ける人々に対して、バウチャー制度によって教育料の負担を軽減することなどで、いわゆる情報化に伴って生じる雇用削減に対してのセイフティネットを構築することが性急に望まれるだろう。なぜならば、情報関連投資の限界生産性が非常に高いにもかかわらず雇用調整が進展しないのは、解雇対象となるホワイトカラーの中高年層の受け皿となるような産業が育っていないということがあるからである。公共投資の拡大に代表されるような建築業への財政的支援によって、失業者の雇用の受け皿を確保することができた一般資本とブルーカラー雇用者との代替の場合と異なって、情報関連投資の雇用代替の対象は特にホワイトカラー雇用者なのであるから、IT関連の再教育などを通じて特にホワイトカラーの雇用に流動性を持たせることも、政府がIT革命の負の側面を吸収するという点で非常に重要な政策であると考えられる。
また、1990年代後半から特に盛んに行われるようになった情報関連投資によって、情報関連資本ストックの蓄積が進んでいるにも関わらず、依然としてこの硬直した企業体質の下、潜在的に限界生産力が非常に高い情報関連資本ストックを上手く活用できていない状況を改善していかなければならない。現在のところ、情報化による雇用創出の効果がそれほど現れてきていないのは、企業が情報化を推進していく際に、業務フローや組織体制そのものが情報関連資本を効率的に利用する形態に変わっておらず、情報関連投資の投資目的が達成されにくい状況にあるためである。こうした状況を改善していくためには、雇用の受け皿を確保し雇用調整コストを低減していくことで、企業の構造改革に対するインセンティブを高めていく必要があるだろう。
情報関連投資の増勢によって高成長を記録した米国の状況とは異なり、現在の日本は依然として低成長の状況にあり、また、情報関連投資の増勢のために不可欠な、雇用の安定という状況が達成されていないということが未だに情報関連投資の効果が強く現れてきてはいない理由である。そこで、新たな雇用を創出するような動きを支援すべく、政府としては情報通信関連分野において成長が期待できる産業への支援を積極的に行うべきだろう。日本は現段階では情報化による生産性の上昇が顕著には現れてはいないものの、このペースで情報関連資本ストックが蓄積すれば、生産面からの雇用創出が期待できる。例えば、規制緩和等を通じて、小規模ビジネスの可能性を支援したり、アウトソーシングやSOHOといったような新しい労働形態を可能にするために労働基準法の改正を行うなどして、彼らにより広い活躍の場を設定することが重要であるだろう。そして、以上のような労働市場に関する問題が解決されていけば、情報関連投資の増勢も本格的なものとなり、日本経済を持続的な成長のための回復軌道に乗せることに寄与できると考えられる。
最後に、直接今回の分析から導き出されたものではないが、日本も米国に倣い、大蔵省や経済企画庁、通商産業省などが「日本版ディジタル・エコノミー」を発表すべきである。IT白書など銘打ち、国を挙げて情報化に向けて動き出さないと、変化のスピードが速い今日において、あっという間に後進地域に追いつかれてしまう可能性も否定できない。また合わせて情報関連資本ストック等のIT関連の統計の拡充をより一層図ることも必要であるように思われる。
【参考文献】
熊坂有三(2000)「情報インフラが米国経済に及ぼす影響」経済セミナー3月号
熊坂有三峰滝和典(2000) 「ITの米国経済への影響―新古典派アプローチ」経済セミナー2月号
篠崎彰彦(1999)「情報革命の構図」東洋経済新聞社、1999
篠崎彰彦(1998)「情報化と雇用に関する日米分析」「国民経済」161号
篠崎彰彦(1996)「米国における情報関連投資の要因・経済効果分析と日本の動向」『調査』
齋藤克仁(2000)「情報化関連投資を背景とした米国での生産性上昇」日本銀行調査月報
中西泰夫・篠崎彰彦(1998)「情報化の実証分析」『情報化の経済効果に関する実証的研究』
松平Jordan (1998)「情報化がマクロ経済に与える影響」『FRI Review』1998
松平Jordan (1998)「日本企業におけるIT投資の生産性」『FRI Review』1999
三和総研リポート「情報革命が生み出す雇用~90年代の米国労働市場の変化~」
富士通総研(1999)「情報化投資に関する調査報告書」
経済企画庁「国民経済計算年報」各年
経済企画庁「経済白書」11年度版
経済企画庁「民間企業資本ストック年報」
経済企画庁「企業行動に関するアンケート調査」1999.4
経済企画庁調整局「日本経済の情報化」1986
総務庁統計局「労働力調査」
通商産業省「通産統計」
労働省「労働白書」11年度版
Erik Brynjolfsson and Lorin Hitt “Paradox Lost? Firm-level Evidence of High Returns to Information Systems Spending”, 1993
U.S. Department of Commerce, The Emerging Digital Economy, 1998
U.S. Department of Commerce, The Emerging Digital EconomyⅡ, 1999
U.S. Department of Commerce, The Emerging Digital Economy2000, 2000